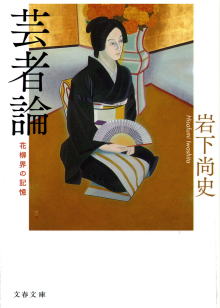著者の略歴−1961年生れ。國學院大学文学部卒業後、新橋演舞場株式会社入社。劇場創設の母体である新橋花柳界主催「東をどり」の制作に携わる。明治生まれの錚々たる名妓たちに親しく接し、幕末から平成にいたる新橋花柳界の調査研究を進め、社史『新橋と演舞場の70年』を編纂した後、97年に退社。06年に上梓した『芸者論 神々に扮することを忘れた日本人』(本書の単行本)にて、第20回和辻哲郎文化貧を受賞。その他、『名妓の資格 細書・新柳夜咄』『見出された恋「金閣寺」への船出』など。 芸者は芸を売る女性であり、映画俳優やテレビタレントと同じ職業人である。 しかし、むしろ春をひさぐ売春婦のように、見られているのではないだろうか。 芸者という言葉から、もう正確な人物像を想像することができない。 それくらい芸者は死語になってしまった。
筆者は、新橋演舞場の社員になったために、芸者たちと付き合うことになった。 というのは、新橋演舞場は新橋芸者たちの、芸の発表の場であり、新橋芸者たちの持ち物だった。 学生上がりのウブな筆者を、高齢の芸者たちは、古くからのしきたりを親切に教えてくれたという。 芸者といえば、吉原をおもう。 しかし、吉原の主人公は芸者ではなく、花魁つまり性を提供する遊女だった。 芸者とは、花魁たちの宴の席で、宴を盛り上げるために、芸を提供する補助者だった。 遊女たちの職種を奪わないために、芸者には厳しい制限があり、着物も地味なものしか許されなかったという。 頭は鬢(びん)を張り出して髷(まげ)の前を割った島田に、平打の笄(こうがい)一本、櫛(くし)一枚、簪(かんざし)一本という 簡素なもの。 吉原芸者のこの姿を、花鳥山水等の図案の打ちかけに総縫いの上着と無垢の下着、髪の上は小間物屋の店のようだと形容された遊女と比べれば、いかに遠慮をさせたかということが分ると思います。 そもそも、身分の別のやかましかった近代以前における服装や髪型は、一目見ただけで、その人物の職掌が分るものでなければならず、めいめいの洒落や酔狂で装うものではありませんでした。オリジナリティなどという観念の種さえないのですから、当り前の話です。 現在の私たちの感覚からは一寸分りにくいのですが、見板創始の際に決められた吉原芸者の容儀は、おそらく男装に近い気分が感じられたに違いなく、客の誘惑を拒否するという表象の形であったように思われます。P76 吉原の芸者だけが、芸者と名のることができたという。 遊女と芸者は、きっちりと分かれており、芸者が春をひさぐことは御法度だった。 しかし、女性がいれば、男性がいる。 芸を売るはずの女性が、限られた男性に春を売ったこともなくはない。 現代だって同じだろう。 明治になって遊女が廃れてしまうと、芸者と女郎の区別が怪しくなってきた。 芸者を1人育てるには、莫大なお金がかかる。 5〜6歳で見習いを始め、琴・三味線や踊りなどを仕込むには、誰かがお金をかけなければならない。 児童福祉法などなかった時代には、小さな子供を働かせながら、徐々に芸を仕込んでいった。 だから芸が身体にしみこんだ。 今では年季奉公など不可能である。
しかし、柳橋と赤坂の消滅につづき、新橋の下火で、関東では完全に崩壊した。 これは芸者に限らない。 伝統芸能は、すべて年季奉公に支えられていたから、もう生命を維持することができない。 ところで、芸者が人間国宝などの名妓になるには、後ろ盾になる旦那が必要だという。 芸者は自立した職業だとはいえ、女性の地位は低いもの。 そのなかで、名をなすには経済的な安定が欠かせない。 そこで、身請けされて旦那をもち、擬似夫婦となる必要があった。 結婚に障害がある場合には、芸者を落籍させて第二夫人として囲うことも流行り、これを権妻と称しました。権妻は現在の愛人とは異なり、明治3年の「新律綱領」では本妻と同じく夫の二等親として認められましたから、大和魂を発揚する男子の甲斐性を誇示するものとして男性同士の間では顕彰され、また彼女たちの粋で高等な容儀は権妻風として大いに流行ったものでした。 この権妻風を戯画化したものが、『吾輩は猫である』に登場する金田夫人であり、漱石は言わず語らずのうちに、彼女が芸者上がりであることを実に上手く活写しています。 しかし、諸外国から未開の蛮風というような異見でもあったのでしょうか、20年後には民法において権妻を親族から除外することが決められ、近代国家としての自覚が漸く身に付いてきた明治31年になって、戸籍面から妾という文字を除くことが定められて、現在のような一夫一婦制が布かれたのでした。P141 現在でも、映画俳優やテレビタレントなどが、役をとるために一夜を共にしたり、誰かの愛人になったり、といった噂がある。 体を使わずに女性が生きていくのは、難しかったのだろう。 しかも、体を売ることは悪いことではなかったのだ。 だいたい主婦という存在自体が、セックス付きの家政婦なのだから、女性に職業がない時代には、体を売らざるを得ないのだ。 芸者は建前としては、芸を売っているのであり、体を売っているのではなかった。 不見転(みずてん)芸者という言葉があるように、体を売った芸者もいたが、それは例外であった。 自分で稼いだ芸者は、税金も払っていたし、気っぷが良かった。 旧憲法の下での女性たちの多くが家という制度に閉じ込められ、父親や夫や子に仕えるべきものとされていた中で、芸者だけは客である男性と対等に会話をし、擬似的ながら自由に恋愛も出来、一般の印象とは裏腹に、社会の中で生きることの出来た、数少ない女性たちであったことも事実である。 また、娼妓と厳しく区別されていた東京の芸者は、芸を以て宴席に興を添えることに対して報酬を得て、経済的に自立しており、家族を養うことも可能であり、もちろんそこには特定の後援者による金銭的な援助や、時としては非合法的な手段も介在することが少なからず見られたことは本稿に述べた如くであるが、いずれにしても、看護婦と教師と女工、あとは女中になるか、髪結い、針仕事でわずかな手間賃を稼ぐしか、女性の職業というものがなかった時代に、並みの男では敵わぬほどの税金を約めていたのは芸者だけであったという事実は、彼女たちが経済的に自立しうる数少ない女性たちであったことを表しており、賤業婦として社会に虐げられるばかりの気の毒な身の上だったという一つの型には嵌められないことに気付いたのである。P269 と、あとがきに書かれているように、芸者たちは自立した職業だった。 そして、売春婦も自立した職業人だった。 そのために、女性に職業がない社会では、自立した女性を蔑視しなければ、女性は男性に従属しない。 男性に寄生する主婦たちを、納得させるためにも、自立した女性を蔑視する必要があった。 職業婦人という言葉にも、どこか蔑視する響きがある。 専業主婦がセックス付きの家政婦でありながら、プライドを維持していられるのも、芸者や売春婦を蔑視する社会があるからだ。 専業主婦こそ、夫である男性の威を借りているだけである。 自分では何の稼ぎもなく、社会への貢献度はない。 にもかかわらず、男性に寄生することが正しいと教育されているので、プライドを維持できるのである。 裏付けのないプライドは、男性社会が芸者や売春婦を蔑視することにって成り立っている。 自分で稼ぐのは、辛いこともある。 ときには厳しい局面もある。 そこで切ない風情を見せもする。 芸者たちは、そうした風情をも、お金に換える強かさを身につけたのだろう。 芸のないホステスとは違って、芸者は芸に生きた職業人だった。 芸者の起源を、坐女さんや白拍子にもとめる導入部は、やや我田引水な感じがする。 しかし、宴席で楽しませるのは、今だって行われている。 そういった意味では白拍子まで遡っても、おかしくはない。 本書は実に真面目なもので、一種の日本文化論である。 (2009.8.7)
参考: 増田小夜「芸者」平凡社 1957 スアド「生きながら火に焼かれて」(株)ソニー・マガジンズ、2004 田中美津「いのちの女たちへ」現代書館、2001 末包房子「専業主婦が消える」同友館、1994 梅棹忠夫「女と文明」中央公論社、1988 ラファエラ・アンダーソン「愛ってめんどくさい」ソニー・マガジンズ、2002 まついなつき「愛はめんどくさい」メディアワークス、2001 J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 ベティ・フリーダン「新しい女性の創造」大和書房、1965 クロンハウゼン夫妻「完全なる女性」河出書房、1966 松下竜一「風成(かざなし)の女たち」現代思想社、1984 モリー・マーティン「素敵なヘルメット職域を広げたアメリカ女性たち」現代書館、1992 小野清美「アンネナプキンの社会史」宝島文庫、2000(宝島社、1992) 熊沢誠「女性労働と企業社会」岩波新書、2000 ジェーン・バートレット「「産まない」時代の女たち」とびら社、2004 楠木ぽとす「産んではいけない!」新潮文庫、2005 山下悦子「女を幸せにしない「男女共同参画社会」 洋泉社、2006 小関智弘「おんなたちの町工場」ちくま文庫、2001 エイレン・モーガン「女の由来」どうぶつ社、1997 シンシア・S・スミス「女は結婚すべきではない」中公文庫、2000 シェア・ハイト「女はなぜ出世できないか」東洋経済新報社、2001 中村うさぎ「女という病」新潮社、2005 内田 樹「女は何を欲望するか?」角川ONEテーマ21新書 2008 三砂ちづる「オニババ化する女たち」光文社、2004 大塚英志「「彼女たち」の連合赤軍」角川文庫、2001 鹿野政直「現代日本女性史」有斐閣、2004 片野真佐子「皇后の近代」講談社、2003 ジャネット・エンジェル「コールガール」筑摩書房、2006 ダナ・ハラウエイ「サイボーグ・フェミニズム」水声社 2001 山崎朋子「サンダカン八番娼館」筑摩書房、1972 水田珠枝「女性解放思想史」筑摩書房、1979 フラン・P・ホスケン「女子割礼」明石書店、1993 細井和喜蔵「女工哀史」岩波文庫、1980 サラ・ブラッファー・フルディ「女性は進化しなかったか」思索社、1982 赤松良子「新版 女性の権利」岩波書店、2005 マリリン・ウォーリング「新フェミニスト経済学」東洋経済新報社、1994 ジョーン・W・スコット「ジェンダーと歴史学」平凡社、1992 清水ちなみ&OL委員会編「史上最低 元カレ コンテスト」幻冬舎文庫、2002 モリー・マーティン「素敵なヘルメット」現代書館、1992 R・J・スミス、E・R・ウイスウェル「須恵村の女たち」お茶の水書房、1987 末包房子「専業主婦が消える」同友館、1994 鹿嶋敬「男女摩擦」岩波書店、2000 荻野美穂「中絶論争とアメリカ社会」岩波書店、2001 山口みずか「独身女性の性交哲学」二見書房、2007 田嶋雅巳「炭坑美人」築地書館、2000 ヘンリク・イプセン「人形の家」角川文庫、1952 スーザン・ファルーディー「バックラッシュ」新潮社、1994 井上章一「美人論」朝日文芸文庫、1995 ウルフ・ナオミ「美の陰謀」TBSブリタニカ、1994 杉本鉞子「武士の娘」ちくま文庫、1994 ジョンソン桜井もよ「ミリタリー・ワイフの生活」中公新書ラクレ、2009 佐藤昭子「私の田中角栄日記」新潮社、1994 斉藤美奈子「モダンガール論」文春文庫、2003
|
|||||||||||||||